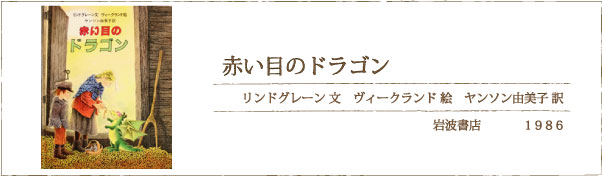かなりの引力を感じた訳は、「Puff」という歌のせいだということは自分で分かっていた。 遠い昔、まだ高校生だった頃、教室の中で友達がギターを弾きながら歌っていた「Puff」というドラゴンの歌。 「Peter Pole and Mary」の有名な歌だ。「puff the magic dragon lived by the sea・・・・」 歌詞を聞いただけでも切なくなる歌だった。「ドラゴン」のイメージは私にとって決して恐ろしいものではなかった。
どんな話だろう。きっとすごいファンタジーに違いない。それともちょっとナンセンスな話か。
帰国後、探しに探したが、見つからない。品切れだった。となると、ますます読みたくなる。図書館に行く。
なかなかない。この本との対面はその後、5年ほど待たなければならなかった。
絵本を手にして、わくわくしながら見開きを開ける。鳥肌ものだ。子どもたちの目はたちまち吸いつけられる。
その見開きを見ているだけで、5分はたつだろう。まだ子どもの、いたいけなドラゴンが、
およそ人間の子どもがとるであろういろいろなポーズで語りかけてくる。赤い目をした、とてつもなく愛くるしいドラゴンだ。
しかし、話の内容はこの見開きから想像するにはかなりかけ離れたもので、心の奥底から切なさがにじんでくるような透明な話だった。
私は、この本を読むたびに泣いてしまう。何度読んでも、涙が出る。子どもたちに読む時も読み聞かせながら、泣いてしまう。

話の内容はドラゴンが出てくるのだから、ファンタジーなのかといえば、
そうでもなく、そこには本当にドラゴンがいてもちっともおかしくない日常が静かに流れているのだ。
全体の文章は、ひとりの女の子が幼い頃経験した出来事への回想の形で書かれている。始まりはこんなふう・・・
「わたしが小さかったころのこと、うちに ドラゴンがいました。」あまりにも静かで真剣な言いように、
「ふーん、そうなの」と素直に耳を傾け始めることになる。「ええ?ドラゴンだって?」などという驚きは一切ないのが不思議だ。
この始まりでもうこの絵本の虜になっているのだろう。その後、進んでいく話は、
この女の子が弟と二人で経験するドラゴンとの毎日であり、淡々とした語り口のせいか、
ドラゴンがいることを素直に認めざるを得ない説得力がある。

二人はドラゴンの面倒を見て、世話をする。好物のろうそくやひも、
コルクを食べさせ、背中を撫で、すねると叱ったり、やんちゃぶりに手をやく。
その毎日は、どこか懐かしいような静かな愛情がにじみでていて胸に痛い。
このドラゴンが、私に忘れていた何かを思い出させるような気がして切なくなる。
終焉に近い赤いページ。どこか遠くに行きたくなるような夕暮れ、夕日に赤く染まったまきばからドラゴンは行ってしまう。
空高く舞い上がったドラゴンが、小さな点になって消えていく。はるかかなたから聞こえてくるドラゴンの歌声は澄み切った
きれいな声だったという。
もうここにくると、我慢も限界。胸の奥が痛くなり、涙が出てくる。なんなんだろう。
![]()
実はこの絵本、子どもたちに読んでも、明らかな反応が得られないことが多い。
むしろ不思議そうな顔つきである。子どもたちはこの絵本からどんな感情を聞き取るのだろう。
私には図り知ることはできないが、望まれれば何度でも、心をこめて読んであげたいと熱望する絵本であることは間違いない。
いや、相手が子どもであろうが、青年であろうが、大人であろうが、そうしたいと思う。
「Puff」の歌は、ドラゴンと友達になり、勇敢に冒険をしたジャキー・ペイパー坊やが成長と共に、一緒に遊ばなくなり、
ついには去って行く。ドラゴンは残される方という訳だが、この絵本はドラゴンの方が行ってしまう・・・・。
最近になって、ドラゴンは子どもであり、親であり、兄弟であり、連れ合いであり、友達であり、恋人であり、
ジャキー坊ややこの兄弟と、ドラゴンの関わりあいの様子は、歌や絵本の域にとどまらず、
世界中のどこででも毎日展開されていると思われる「育てる」という行為なのだと思えてきた。年のせいだろうか。