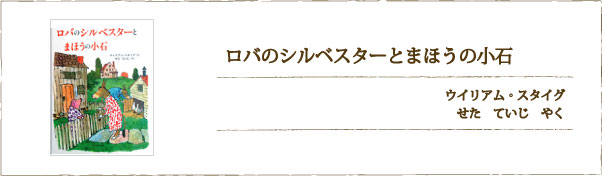
| 自分で何度も読むうちに、わかったことは、実に丹念に作られた話であるということだ。文章は大変わかりやすく、話が次々に連なって流れていく。疑問に思うところもないし、不自然なところもない。子どもは、お話の途中で「なぜ?」や「どうして?」の疑問が少しでもあると、頭の中でイメージすることが停滞して、話が中断されるらしく、お話に乗れなくなってしまう。この作者は、そんな子ども達を、引き連れていく術を十分に心得ている。 |
 |
どうしてロバのシルベスターが、赤くて丸い小石を拾ったのか、どうして偶然拾った小石が、魔法の小石だとわかったのか。そして、かわいそうなシルベスターが、どうしても石になるしかなかった訳も、どうしてももとのロバに戻れない訳も、しっかりと、しかも自然体で納得させていく。私達の方こそ、魔法にかかったようにどんどんお話についていくしかない。 |
| 文章は短く、事実を淡々と述べていき、物静かで、説得力がある。決して、大げさな言葉では書いていないのに、子どもが行方不明になってしまった、ロバの両親の深い悲しみが、十分胸に痛い。手を尽くして探しても、どうしても見つからないことも、悲しいながら、受け入れるしかない。子ども達は、もう泣きそうだ。このあたりは、ドラマチックの極みだと思っていた。
しかし、最近気がついたのは、ここまでが、最もドラマチックな場面へといざなう必然的な道筋だったということだ。 |
 |
| 次のページから始まる3ページの情景は、ゆっくりと、見るものの感情をうねらせていく。物言わぬ岩になったシルベスターが過ごす一年あまり。同じ場所で、岩としてうずくまるシルベスターのまわりで、季節は巡り、月日は過ぎていく。秋の紅葉、降り積もった雪、草木が芽吹く春の景色の中で、シルベスターが、自分の状況を受け入れながら、だんだんと本物の岩になっていく。これ以上のドラマチックな成り行きはない。今度は、読み聞かせているこっちが泣きそうだ。絵は美しい水彩画のタッチで、四季の彩りが胸に食い込む。
シルベスターは、どうなるのだろう・・・・。 |
 |
| ドラマチックな絵本とは、ものすごい冒険物語だったり、考えられない不思議な話だったり、ものすごい感動物語だったりするわけではないこと、大げさな表現や言葉で、読むものをあおるものではないということを、この絵本の力によって思い知った。 |
| スタイグは、ロバの両親のうらやましい夫婦仲と子どもへの愛情に基づいて、最後まで丹念に、順を追ってお話を進め、暗い海のようにうねった感情を、南国リゾートの明るい波のようにドッパーン!と、爆発させるような明るい結末で、終わってくれている。
「よかった。もう・・・どうなるかと思ったよ。」という子ども達の感想に悦に入り、「もう一回読んで」のリクエストにホイホイと応じてしまう。 |
 |
 |
 |
| このお話は、不思議な魔法の小石が重要な役割を果たしている。昔話によく出てくる「願いが叶う」系の要素は、確かにもっている。しかし、近頃流行りの「魔法」を振りかざした話ではない。ウイリアム・スタイグが、子ども達に語りたかったのは、日常生活の中での、もっとひたむきで普遍的な、幸せの見つけ方なのではないかと思う。
それをロバやブタや犬に託して、子ども達に丹念に話して聞かせているのだ。 |
 |
| この絵本は、30年以上前に出ているが、私が、最初に手に入れたのは、10年ほど前になる。2006年には、新版が出版された。新版は、ひとまわり小さくなっており、表紙の字の色が変わっている。見開きには、たくさんの小石を散らした工夫が加えられている。見開きフェチの私としては、ちょっとうれしい。
また、この新版の最後のページには、ウイリアム・スタイグのコールデコット賞受賞スピーチが書かれてある。これを読んで、「うんうん」と首が痛くなるほどうなずきながら、赤線でも引きたい気分になってしまった。子ども相手だからといって、絵本の仕事を軽く見ず、芸術として捕らえている作者の話は、大変分かりやすい絵本論である。子どもたちに、敬意をはらうことができる数少ない大人の一人であり、子どもにとって何が必要なのかを、大真面目に考えているこの作者の、静かな主張に感動する。これは、必読である。 |
| 私個人としては、今まで、迷いながらも、やってきたこと、考えてきたことを肯定された気がして、子ども達に絵本を読み続けていく勇気が湧いてきた。 |



