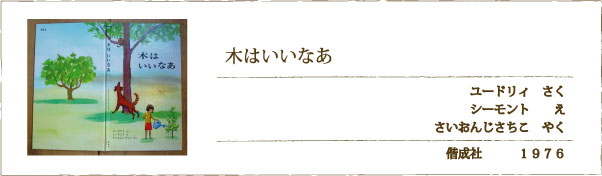
|
この絵本はちょっと形が変わっている。縦長で細く、なんだかスマートな木のイメージ。表紙の絵からして地味な雰囲気で、近頃のお母さんたちの気持ちを動かすことができるかといったら、そうでもないかもしれない。しかも、表紙を開いた1ページ目の、タイトル前に描かれている絵は、海岸に生える一本の松の木のような木。タイトルページは、絵本には珍しいモノクロのページになっている。これでは、一見面白そうな絵本だと確信するには至らないだろう。
でも、この絵をよく見てもらいたい。モノクロでも迫力の絵を。私は、このタイトルページに描かれた木にすごく惹かれてしまった。 本編の衝撃の1ページ目は森の絵。べったりの緑が現れる。そうか、この緑へのアタックのために、タイトルページをモノクロに抑えたのか・・・・。効果絶大だ。次は川べりの倒れた木の絵。またモノクロに戻る。そしてまためくると、遠くの緑の森がカラーで広がる。 ここから先、常に、モノクロページと見事な色彩ページが、交互に現れていく。色彩ページで、息を吸い込み、モノクロページで、息を吐く。深呼吸のような、とても心地よいリズム感に引き込まれる。画家シーモントが、作者ユードリィの文章を生かして、よくよく計画した場面運びだといえる。 よく見ると、色彩ページには、色を入れて表現した方がいい訳がある。べったりの森の緑、紅葉の黄色や赤、りんごの実の赤、野原の花の水色や白、木陰の深い緑、雪嵐の白。深呼吸をしながら、どんどん木の魅力にとり憑かれていく。どのページにも色がついていたらいいのに、なんて絶対思わない。むしろモノクロのデッサンタッチがかえって木の美しさを際立たせているような気がしてくる。 |
 |
| 特に、大きな木で遊ぶ子供たちの様子は、モノクロゆえに、すごく活き活きとして、木との一体感がある。この場面は、子ども達の人気の的だ。この木はいい!こんな木があったら、絶対に登ってみる。
ユードリィの文章は、ずっと、どんなに木がいいものかということを、繰り返し話している。この絵本は物語形式ではない。題名のとおり、どんなに木がいいものかということ説得しているといった方がいいくらいだ。次々と、「木はこうなんだよ。ああなんだよ」。と、そう、まさに説得としか言いようがない。しかも、深く静かに潜行する説得だ。「そうか、木っていいものだなあ」と、しみじみと思わせて、木を植えなきゃと決心させる。すごく率直な絵本だ。 |
 |
私には、木についての思い出がいくつかあって、この絵本を読んだあとには、それが、よく頭に浮かぶ。その中でも、この絵本の4場面目に出てくる「たった1本でも、木があるのはいいなあ。」という、ワンフレーズが、フラッシュバックのように、一本の桜の木を思い出させる。
自分が植えたわけではないが、我が家の庭に木を持っていたことが一度だけある。 イギリスにいた頃に住んでいた家の、玄関の前とバックの庭に、一本ずつ桜の木があった。まだ若い木で、倒れたり傾いたりしないように、幹が添え木にゴムのベルトで、結わえ付けられていた。とってつけたように、庭の真ん中に立っているものだから、初めて見たときには、なんだか奇妙な感覚だったが、我が家の木だと思うと、たちまち愛着が湧いた。年々成長して、花も咲くようになり、小さな実がなるときには、ブラックバードが食べにきた。4年後には、幹は、添え木よりもずっと太くなって、とうとう結わえ付けていたゴムは切れてしまった。 |
| やがてその木は、当時あちこちの庭や公園の木登りを実践していた娘や、その友達の愛着を誘い、木登り用になったのはもちろん、あるときは、鉄棒とペアで、小屋つくりの骨組みになり、あるときはバトミントンのネット代わりの紐が縛り付けられ、いろんな意味で、かなり役に立ってくれたように思う。日曜日に、木の横にテーブルを出して、家族でお昼を食べたり、夫を椅子に座らせ、首に風呂敷をかけて散髪をしたりした。ちょっとした癒しの空気もあった。 最近になって、娘が白状したところによると、木の上に鳥の巣をつくって取り付けたことがあるという。鳥は、巣を小枝や藁に泥や土を混ぜてつくるということを、学校で教えてもらったことがあったとかで、友達と、おわんに泥をつめて穴をあけて巣のようなものをつくり、木に登って、枝の間に取り付けたというのだ。「残念だけど、鳥は入ってこなかったわ。当たり前よね。結構待ってたんだけど。」と、娘はいたずらっぽく笑う。あきれた。そんなことまでしていたとは知らなかった! あの桜の木は、娘が出張の折に、16年ぶりに訪ねていったとき、跡形もなくなっていたという。 |
 |
| 木にまつわる思い出がなにかしらあるのなら、思い出してみるのもいいのではないだろうか。この絵本と共に。 |



