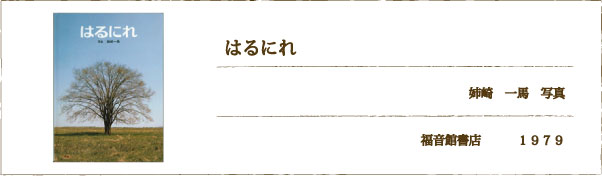
| この絵本は写真絵本の傑作である。想像できないような光景にあっと驚きながら、最後まで目がそらせない。耳のそばで、時間が走っていくのを感じながらも、身動きができないような硬直感を感じる。最後には、遠い旅をしていたような感覚が襲ってくる。子どものみならず、大人の目にも衝撃が及ぶはずだ。
始めは、このような写真絵本を子供たちの前に広げることを想像すると、かなり心もとなくなった。どう読んだらいいか、分らなかったからだ。 文章はない。高名な自然写真家による迫力の写真には、撮った本人の自然観が込められすぎていて、その情景は、文章ではとても表しきれないだろう。この写真を文章でどう語ろうというのか。これはもう、何度も見せるしかない。ゆっくりめくってみる。早くめくってみる。遠くから見せてみる。間近で見せてみる。何か補足して説明を加えてみる。いろいろとやってみたが、自分の考えすぎだとだんだん分ってきた。そんな小細工は無用なのだ。そのうち、ページをめくりながら子ども達との一体感を感じ始めた。かける言葉なんていらなくなる。めくるタイミングは子ども達任せにして、自然に絵本の中の木を巡ればいいのだ。そんな自然体でいることが、何より大切なことだと、この絵本を前にして痛感した。 |
 |
 |
| 始めの場面、野原に木が立っている。広い空が広がっている。狭い部屋から一気に、どこか遠い星にワープしたような感覚。静かだ。しばらく見渡していると夕暮れになる。2場面目で、夕暮れの木にちょっと近づいてみる。ちょっと寒くなってきた。静かだ。めくって3場面目、ヒューヒューと雪が降ってきた。ぐっと木に近寄ってみる。それに答えるように木がざわめき始める。見上げると、視野からこぼれるほどの枝の広がり。すごい生命力に圧倒されて思わず後ずさる。周りはすっかり雪に覆われての4場面目。寒い。少しの身じろぎもしないで、枝の先までしっかりと、しかもしなやかに立っている木に、力の意識が流れている。木の自己主張。5場面目、夜がやってくる。この空気の色、孤独だ。朝がくる・・・・・
ページをめくるごとに、アングルは変わり、見ている方が心に覚える感情は変化する。不安感、孤独感、爽快感、充実感。力強さ、優しさ、おだやかさ、希望、・・・・一本の木の生き様が画面の中でひとつの宇宙をつくる。 |
| 最後には、枝の先端の先端まで葉っぱが伸び、誇らしげに立っている「はるにれ」がドーンという効果音と共に現れる。この木の本物を見てみたい。。 |
| 私が子どもの頃、学校の教室にカレンダーが貼ってあって、その中のひとつの風景写真に衝撃を受けた。その写真からしばらく目が離せなくて、多分、私は、呆けたように口を開けてそれに見入っていたに違いない。山の上に建っている、きれいな外国のお城の写真で、まるでおとぎ話に出てくるようなお城だった。「ほんとにこんなお城が現実にあるものなんだ・・・」その写真は頭の中に刻み込まれて、離れなくなった。ドイツのノインシュバインスタイン城である。
その後なぜか、たびたびこのお城の写真に遭遇することがあり、そのたびに特別な思いが湧きあがっていた。 高校の美術の時間に、写真をもとにそのお城を必死でイラストに描いたこともある。確か、課題はレコードジャケットのデザインだった。本物を見たくて見たくてしかたなかったが、赤いほっぺの田舎の女子高生には、夢のまた夢であった。20年後、何が幸いしたか、ついに、本物のノインシュバインスタイン城の前に立つことができたときには、これまた、あんぐりと口を開けて棒立ちだったと思う。昔見たあこがれの写真どおりの夢のようなお城だった。願いは叶うものなのだと、ここまできた自分の人生に喝采を送った。 |
| 一度見た光景が、その後の価値観の一端を担うこともある。一度の出来事が、希望の芽になることもある。一枚の写真に惹かれて始まる人生の一端があるかもしれない。ああ、恐ろしい。 子どもに何を見せてやりたか。こんなことを真剣に考えたことはあるだろうか。 |
 |



