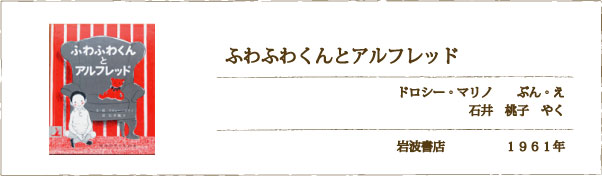
| この絵本は、かなり古い。「岩波の子どもの本シリーズ」の中の一冊で、40年以上も前に、出版されたことになる。しかし、古さは感じない。まことに不思議な雰囲気をもつ絵本である。シンプルで色味も少ないが、とてもよく考えられた、絵と文章の配置に恐れ入る。私が特に好きなのは、ふわふわくんとアルフレッドのツーショットが描かれてある表紙である。写真館でよく撮るような、椅子を介しての記念写真のようだ。椅子の背に題字がいい具合に配置されている。この椅子は、お話の上では、とても大事な小道具になっている。憎い演出だ。バックは、赤に白の縞模様で、主人公ふわふわくんと、持ち主アルフレッドの家の、壁紙の模様ときている。まったく気が利いている。 表紙をめくると、見開に、欧米によくある肖像画が、これまた縞模様の壁に並んでいる。登場人物紹介といったところだろう。絵本は、表紙からお話が始まるというのが、私のモットーだが、この表紙と次の見開きは、子ども達を、たちまちお話に誘い込んでくれるはずだ。 次の題字のページには、やんちゃなアルフレッドと、訳知り顔のふわふわくんの、リラックスした記念写真。ステキな縞模様の壁紙に、ステキな長椅子。二人の距離感に、「teddy bear」とその持ち主の、心温まる甘い話・・・とはいかないこのお話の展開が垣間見える。 |
 |
 |
| 表紙も見開きも題字のページも、絵は、アルフレッドがふわふわくんを、抱いてかわいがっている絵ではない。二人は、対等の関係のように見える。これは、かなりのミソだ。 お話は、この二人が、この絵のような、穏やかな対等の関係になったいきさつを、語っているということになる。決して甘ったるい話ではない。 |
| ふわふわくんは、おもちゃのくまだ。赤ちゃんのときから、いつもアルフレッドと一緒にいた。しかし、アルフレッドは、確実に成長していく。自分の世界が、だんだん広がっていくアルフレッドに、新しいおもちゃが届く。トラのぬいぐるみ「しまくん」だ。新しいだけに、きっと、毛並みもきれいでやわらかいことだろう。それにくまよりも強いと思われるトラなのだから、男の子が惹かれるのも無理はない。 それからというもの、いつもふわふわくんがいた場所は、椅子もベットもしまくんの居場所となり、ふわふわくんは、おもちゃばこの中に放置されることになる。 正直いうと、子どもは日常、平気でこういうことをする。でも不思議なことに、絵本を前にした子どもたちは、それを客観的に見ているせいか、ふわくんに同情し、逆に、アルフレッドに批判的になる。「ふわふわくんが、かわいそうだよ」とか、「アルフレッドいけないよ」とか。 |
 |
| 果たして、ふわふわくんは、この運命を甘んじて受け入れるのだろうか・・・。さあ、あなたが、ふわふわくんだったらどうする? 泣き落としてもとの地位に返り咲くか、人の手を借りてしまくんを葬り去るか、報復行動に出るか、アルフレッドの情を信じて待つか。きっぱりと見切りをつけて、さっさと新しい道を探すか。 |
| ふわふわくんは、思いがけない行動に出て、アルフレッドに敢然と立ち向かう。勇気あるくまの最初の行動は、大人でもハッとさせられる。「どうして、ぼくと遊んでくれないの?」と訴える。この素直さはどうだ。真っ直ぐにストレート直球勝負。けれども、そう簡単に事は好転しない。 考えたふわふわくんは、次の一手を打つ。もともと自分の持ち物で、言うとおりになると思っていたものが、突然言うことを聞かなくなったら、誰だって動揺する。相手の心理を読んだ頭脳プレイで、アルフレッドと駆け引きしていくこのくまは、ただ者ではない。どのような駆け引きなのかは、ここで明かしても詮無いことだ。読んだ者にしか分らない。 確かなことは、ついに、ふわふわくんは、元のようにアルフレッドの「teddy」の地位を取り戻すということだ。おまけに、しまくんも一緒に。ちょっと以前と変わったことは、アルフレッドと、甘ったるいだけではない対等の関係になったことだ。 これが、表紙や、題字のページの絵のあるような、ツーショットのいきさつだったのだ。 |
| 古い話だが、私が子どもの頃に、初めて買ってもらった人形は、セルロイドの人形だった。頭にでこぼこの茶色い筋が入っていて、それが髪の毛だった。それでも、寝かせると目は閉じるし、起こすとパッチリと開いた。子どもにとって、人形遊びは毎日のことで、近所の友達と、それぞれの人形を持ち寄って遊ぶときには、自分の人形が一番だとは思いながらも、友達が、新しいのを持ってくると、羨ましかったりもした。 小学校高学年のとき、私にとっては「一大人形事件」が起きる。東京に住んでいたお金持ちの伯父夫婦が、初めて田舎に帰ってきたとき、高知で一番のデパートで、大きな新しい人形を買ってくれたのだった。恐ろしくきれいな人形だった。髪の毛は金髪のロングヘアー、目は青く、透き通るようなきれいな肌色をしていた。天にも昇るような気持ちで、触るのも畏れおおい気がしたのを、今も感覚的に覚えている。 そして、家に帰って、いつものセルロイドの人形をふと見たとき、人形が、悲しそうな顔をしているように思えて、その毛のない頭をなでてやったのも、覚えている。けれども、それ以来、一緒に遊びに連れて行くのは、やっぱり、金髪の人形の方だった。 セルロイドの人形は、反撃さえしなかったが、捨てがたく、本棚の上に座らせていたが、埃をかぶっていたことは、否定できない。いつの間にか、いなくなったということは、どこかの引越しの時点で、母が捨てたに違いない。長いこと世話になったお礼さえ言わなかった・・・・。 |



