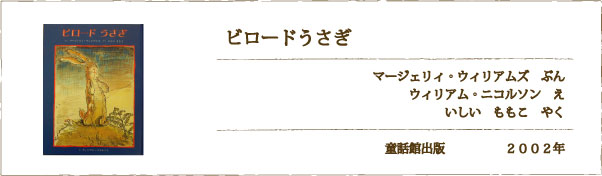
| この本は、絵本というよりも、挿絵つきの物語の本である。 2002年に童話館から出版されたものだが、もともとは、とても古い絵本で、1922年に、イギリスで出版された。 マージョリィ・ウィリアムズによって書かれ、挿絵はウィリアム・ニコルソン。第3回で紹介した、あの「かしこいビル」の作家である。 イギリスで出版されたこの本が、童話館から原型に近い形で出たとき、私としては、かなりの喜びだった。 |
 |
| 渋い紺色の表紙に、飾り文字の題字。裏表紙には、ほのかに揺らめくろうそくが描いてある。
その横にある「The Velveteen rabbit」の文字が、やけに神聖さをかもし出している。 読んでみて、一番に感じたのは、文章の美しさである。本当に自分が恥ずかしくなるくらい、美しい言葉で語られているということだった。 石井桃子さんが、訳した文章は、近頃めったにお目にかかれないような、美しい日本語を、認識させてくれる。この絵本の語りようは、 特別な世界観を持っているように思う。「ムギと王さま」を書いたファージョンの文学にも似た「お話を語る」ことの根源に迫るものである。 |
 |
| 例えば、肩掛けを羽織った、年とったおばあさんが、子ども部屋で、お気に入りの人形を抱えた、 寝巻き姿の2,3人の子ども達を前に、ゆっくりと、静かに話して聞かせる光景。または、髪の毛を、絹のリボンで、ふんわりと耳の横で束ねた 、美しい女性が、ベッドに寝ている子どもの頭を、なでながら、やさしく語っている光景。そういったイメージに、完全に支配されてしまう。 子ども部屋の人形たちに起こった不思議なお話を、現実と空想の狭間で揺れながら聞いている、子ども達の心情を想像すると、物語の崇高さを感じる。 |
| 主人公は、ビロードでできた、きれいなうさぎの人形。クリスマスに、ぼうやにプレゼントされた、おもちゃのひとつだった。 子ども部屋には、いろいろなおもちゃが住んでいて、それらは、それらなりの特徴的な個性を持っている。そして、おもちゃには、おもちゃなりの社会がある。 最新式のおもちゃたちは、自分は本物であるという自信に満ちている。だが、うさぎは、自分の体の中には、おがくずが詰められているというコンプレックスから、 本物ではないと思っている。悲しいうさぎの願いは、「ほんとうのもの」になるということだった。 |
 |
| ある日、うさぎは、子ども部屋に昔からいる「木馬」に、「ほんとうのものになるということ」についての話を聞く。
この木馬は、「ほんとうの馬」になっているという。うさぎと木馬の話の内容は、単におもちゃの話ではなく、人の心の有りように及ぶ、深い話だ。
ページを、何度もめくり直しながら、読みふけってしまった。子どもたちと人形の関係を、こんなふうに考えていた、この作者の、及びもつかない教養の深さと、
子どもたちへの愛情の深さを、覗き込んだような気がした。 かしこい木馬は語る。「ほんとうのものになるというのは、わたしたちの心と体に、何かがおこる、ということなのだ。」うさぎは、それが、 どういう意味なのかは、理解できない。また、「ほんとうのものになるには、苦しいことも、たくさんあるのだ。」とも語る。うさぎは、 「苦しいことなしに、なれればいいのに」と思う。 この伏線ともいえる木馬の語りは、これからのうさぎの行く道を、しっかりと裏付けていくことになる。 |
| うさぎは長い年月をかけて、「ほんとうのもの」になっていく。 ビロードはだんだんに擦り切れ、みすぼらしくなり、しっぽはとれてしまう。鼻は剥げて、ひげは抜け落ち、茶色だった体は灰色へと変わっていく。 しかし、木馬の語った話のとおり、「ほんとうのうさぎは、みすぼらしいなんてことを、少しも気にしない。」のだった。そして、その先にうさぎを 待っているものは、幸せか、不幸せか・・・・。 お話の最後は、イギリスらしく、フェアリーの登場で幕を閉じるわけだが、最初のイメージのとおり、子ども部屋に起こった、不思議な魔法の結末は、 子ども達には、余韻を持たせる完璧な終わり方である。この私も、かなり、やられた。 |
| 我が家にいる、おどろおどろしいまでに変貌をとげた、キティちゃんのぬいぐるみは、確かに、娘によって「 ほんとうのもの」になっているのだと思う。もちろん、毛ははがれている。耳は片方が半分になっている。黄色だった鼻は、フェルトが破れ、 黒いプラスチックの中身が丸出しになっている。首は何度も修理したため、角度が普通じゃない。破れが激しく、原型を留められなくなった下半身は、 ある時点で、祖母が、まるごと白いジャージ生地で覆って修理した。手は片方が小さい。白いはずのぬいぐるみは、今はグレーだ。いや、かなり、黒に近い。 |
 いつから、キティちゃんは、「ほんとうのもの」になったのだろう。貴重な証言がある。
娘が、友達の家の庭で、かくれんぼをしていたときに、キティちゃんを、置き去りにして、家に帰ってきてしまったことがあった。夜になって、忘れたことに気がついた娘は、半狂乱になって泣いた。
その晩、友達が、その庭で見つけてくれたのだが、木や草花が、生い茂る広い庭の中で、キティちゃんが横たわっている辺りが、ぼうっと白く光っていたという。まるで、オカルトだが、その友人曰く、「本当よ。ほんとに、キティちゃんがいた藪の周りが光っていたのよ。」
そのときすでに、キティちゃんは、「ほんとうのもの」に、なりつつあったのだろう。 いつから、キティちゃんは、「ほんとうのもの」になったのだろう。貴重な証言がある。
娘が、友達の家の庭で、かくれんぼをしていたときに、キティちゃんを、置き去りにして、家に帰ってきてしまったことがあった。夜になって、忘れたことに気がついた娘は、半狂乱になって泣いた。
その晩、友達が、その庭で見つけてくれたのだが、木や草花が、生い茂る広い庭の中で、キティちゃんが横たわっている辺りが、ぼうっと白く光っていたという。まるで、オカルトだが、その友人曰く、「本当よ。ほんとに、キティちゃんがいた藪の周りが光っていたのよ。」
そのときすでに、キティちゃんは、「ほんとうのもの」に、なりつつあったのだろう。今は、これ以上のダメージを防ぐために、クローゼットの中に、大切にしまわれている、この「ほんとうのもの」になったぬいぐるみの前に、いつか、フェアリーは、現れるのだろうか。 |
| 「子ども部屋には、時々不思議な魔法がおこる」というくだりがある。
イギリスでは、産業革命以降、絵本があるような裕福な家庭には、大人とは区別された「子ども部屋」があって、
子ども達は常にその部屋で生活するようになっていたらしい。そして、「ばあや」や「家庭教師」といった母親以外の専門家が、
子ども達の普段の面倒を見ていた。これはこれで、一つの子どもの生活文化の歴史だといえる。このお話はこのような背景があってこそ、
生まれたのではないかと、思う節もある。 ピーターパンやメリーポピンズも、子ども部屋に起きた、不思議な魔法の話といえないだろうか。この機会に、子ども部屋を見直したいような気がする。 |



