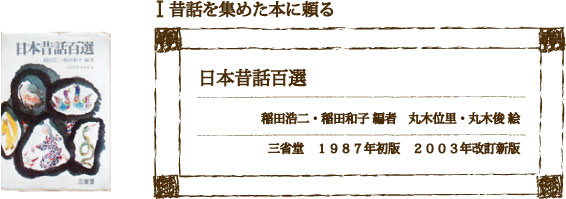
| 百選という名のとおり、きちんと百話載っていて、日本各地からのお話が、「北国」「中の国」「西国」の三つに分けて配列されている。 昔話は、その土地独特の雰囲気を包み込んでいて、風土を背負ったものである。この本の昔話は、そこを非常に大切にしていることに、まず感心する。 地域性を大切にしているとはいえ、言葉は、標準語に近く、分りやすいのがいい。それでいながら、ところどころに、昔話の語り調子や、ある程度の方言を、実に快く残しているのがいい。 読んでいるうちに、自分が「語り婆さ」になったような気がしてくる。 |
| 昔話は、いろいろな地方に伝えられていて、その土地の言葉で語るのが、最も雰囲気がでるものだと思うが、どの地方の方言でも、使いこなせる人は、そういないだろう。私は、四国や関西で暮らした経験があるので、その方面の言葉なら、なんとかそれらしく語ることはできる。 ところが、不思議なことに、この本は、他の知らない土地の方言でも、すんなりと読み聞かせていける。もちろん、前もって、練習はするが。 昔話の原話を、言葉のバランスを考えながら、ここまで楽しめるように書きまとめた著者の苦労は、はかり知れない。 |
| 「今日は、どの話にしようか・・・」とおもむろに本を開く。ひとつお話をする。「もっと、もっと」とせがまれるままに、次々とお話をしていくうちに、夜が明けそうだ。 |
 |
| 昔話では、信じられないことが普通に起こる。起こった事件は解決され、失望や希望、恐怖や幸福が繰り返されていく。生と死が頻繁に入れ替わり、正直も騙しも包み隠さず、あからさまに入り乱れる。ユーモアの隣に残酷があり、裕福と貧乏が隣り合わせる。因果応報もあれば、土着の畏怖も見え隠れする。 昔話には、遠い祖先が語りついできた、人生のエッセンスがつまっているのだ。 |
| この本の「まえがき」に、はっとさせられる、深い一文がある。 「昔話の語り手の心は、遠い過去を背負いながら、未来に向かって進んでおりました。」 とても、そんな重い役割を背負って、昔話をすることはできないが、肝に銘じながら「語り婆さ」になっていきたいものだ。 |



