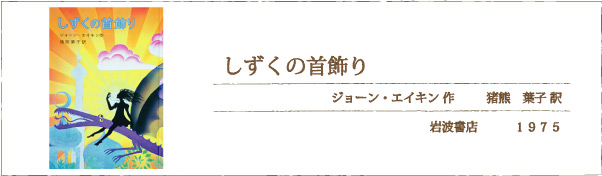
| その中の一冊「しずくの首飾り」は、ジョーン・エイキンという作家が書いた珠玉のファンタジーが、8話収められている。どの話も、昔話のようで、身近にありそうなドラマのようで、SFのようで、学園もののようで、・・・ 作者の、何者にもとらわれない自由な発想と、羽がはえて飛んでいきそうな躍動感が満ち溢れている。もしも、私が小学生の時にこの本に出会っていたら、それはもうこの話の虜となり、夜、布団の中で、「もしもこうだったら、ああだったら・・」と空想する世界は、かなり飛躍的な発展を遂げたに違いない。 |
 >
>
| 箱入りの本はうやうやしく箱から出すところからが、読み聞かせである。出してみると、この本の表紙の絵は、裏表紙まで続いている。鮮やかな色のおとぎ話の世界をバックに、ハイセンスな黒い影絵が配置されている。この装丁は、岩波書店の箱入り本の中では、群を抜いて美しい。作者ジョーン・エイキンの頭の中の空想世界は、きっとこんなだろう。箱の中にこんな美しい絵が潜んでいるとは、まるでびっくり箱のようではないか。 |

| 見開きのイラストは、この本に出てくる、物語の主人公を、一堂に集めたファンタジー世界に仕上がっており、「さあこれから、おとぎ話のはじまり、はじまり」と拍子木を打っているような、見事さである。本を全部読み終わったら、絶対にまた、この見開きを開けて、見直したくなる衝動にかられるのは、間違いない。 「しずくの首飾り」の本の中には、8つの物語が収められているが、本の題になっている一番最初の物語は、読んでいて、途中で絶対に「この続きはまた明日」にできない。最後まで読まないことには、どうなるのか心配で寝られない。結末が分かっていても、何回でも読みたくなる。 |

| 物語は、主人公となる女の子の父親が、北風と出会うところから始まる。父親は、木にマントを引っ掛けて、身動きが取れなくなった北風を助けたことで、娘に、不思議な贈り物を授かる。日本でも、アジアでも、欧米でも昔話によくある恩返しもののパターンである。 しかし、その贈り物のなんと素敵なこと。1つ年をとるごとに増えていく「しずくの首飾り」だというから、女の子にとってはたまらない魅力だろう。もちろんこれは、単なる素敵なアクセサリーではない。ひとつしずくが増えるごとに、少しずつ魔法の力が増えていくというところが、読む側の心を、ざわめかせる。 魔法といっても、欲張りな大人が考えそうな物欲を満たすための魔法でもなければ、人をどうこうできる征服欲を満たす魔法でもない。日常生活の中のほんの些細な魔法だ。日常生活に少しばかりのエッセンスが加わると、とても素敵な人生になるということだ。だが、考え方によっては、自然を左右できるすごい魔法といえる。なにしろ、贈り主が北風なのだから。 |

| 毎年1つずつ少しの魔法が加わりながら、しずくはテンポよく増えていくが、もうすぐ10個揃うと言う時、主人公の女の子が、首飾りをなくしてしまうことから、物語は大きく動きだす。ここからは、意地悪な友達が出てきたり、いろいろな生き物が助けてくれたり、かなりのドラマとなっていく。最後の方に、アラビアの王さまやお姫さまがでてくるあたりは、もうファンタジーの面白エッセンスのオンパレードだ。 |
| 作者の空想力、想像力はどのようにして湧き出てきたのだろう。確かに、イギリスは、ファンタジーの宝庫だ。大昔から、木や花には妖精が宿り、空にはドラゴンが飛び、地にはエルフが踊り、地中にはゴブリンやドアーフが潜む国である。そういう環境が育んだ技であるのか。ジョーン・エイキンの短編は、決して重厚なものではない。ひとりひとりの子どものすぐそばにあるという存在感を持ち、「こうなればいいなあ」という幼い子どもの望みをみごとに満足させてくれる。 「しずくの首飾り」の8話は、子どもによって、はまる話が違う。それは、子どもの生活体験がそれぞれ違い、理解できる範囲が違い、「こうなればいいなあ」の事柄が違っているからなのだろう。こうなると、物語の読み聞かせは大変興味深いものになってくる。 絵は挿絵となり、読み聞かされた方は、頭の中で言葉からの映像化を活発に行わなければならない。初めに言葉ありきである。 物語の理解は、子どもの想像力に頼るということだ。言葉によるイメージつくりは、とても個人的なもので、多種多様。生活体験の多い子ほど、言葉からの映像化がたやすいことは確かだろう。いろいろなことを空想するには、頭の中に空想の種があるということだ。 物語を聞いているときの子ども達の頭の中はどのように働くのだろう。 |
| ここにもう一冊の「しずくの首飾り」がある。 つづく… |



