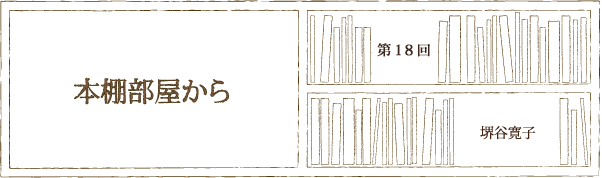|
| 「ポケット版学研の図鑑」 : 学習研究社 |
| 子どもたちの、夏休み最大の懸案事項は、夏休みの宿題である。特に自由研究は、親も頭を抱える課題だといってもいいだろう。 今でもよく覚えている。私が取り組んだ自由研究は、「雑草の標本」「葵の花の咲き方」「影の研究」「シロアリの研究」。自由研究は、本来、 子どもが自分から、興味の目を向けたものへの疑問で始まるべきだろうが、どうしてこんなものを研究したのかは、覚えていないから、多分母に すすめられたか、先生に助言を受けたかである。 「雑草の標本」では、家の庭やら、田んぼのあぜ道やら、その頃はやたらにあった野原で、これはなんだ?という雑草を、根っこから取ってきて、 押し花にした。この題材を選んだのは、確かに母の陰謀だったのではないか思う。家の庭の草取りをすれば、それだけでも、結構たくさんの植物が 収集できたのだから。押し花ができたら、画用紙に貼って、名前を調べる。当時は、植物図鑑など、家にあろうはずもなく、標本を抱えて、バスに 乗り、大きな図書館に調べに行った。高知市立図書館のシーンとした冷たい油拭きの床と、気難しそうな司書のおばさんの、トーンを落としたコソ コソ声が、自分を博学にしてくれそうで、その場にいるだけでも意義があるように思えたものだ。 いろいろな植物の写真や絵を見ていると、別の宇宙があるようで、「図鑑イコール勉強」と思っていたのが、なんだ、写真や絵ばっかりで楽しい じゃないか。と思えてきた。 「シロアリの研究」では、そんなマニアックなものを、よくもまあ調べたものだと、今思うが、これもまた母の陰謀ではないかと思う。なんせ、 家の外の塀に、シロアリが、思うがままに巣くっていたのだから、採集に行く必要もない、お手軽材料だった訳だ。捕まえてきて、虫眼鏡で見て スケッチした。あの白と茶色のシロアリが、虫眼鏡を通して、妙にきれいだなあと思ったものだ。いろいろな食べ物を与えてみたりもした。 種類を調べるのに、これまた、図書館に行って、百科事典やら虫の図鑑を調べる。百科事典は意外に面白くなかった。文字ばかりだったからかも しれない。 けれども、図鑑の方は、見ていると飽きなかった。当時、図書館にあった図鑑は、かなり分厚く、目的のものを探してページをめくるのも、エネルギーがいった。しかし、ある意味、絵本と同じ楽しみ方ができていたように思う。いわば夏休みは、期間限定ではあるが、図鑑と向き合う大事な季節だったかもしれない。 …つづきへ |
 |
| 「絵本図鑑シリーズ」 : 岩崎書店 |
| この「絵本図鑑シリーズ」は、私が、幼児教育の仕事をするようになってから、手に入れたものである。 子どもたちを教えていて、最近特に、強く思うことは、都会に暮らす子どもたちが、本当の野原を知らないということである。季節の花や、虫の名前を知らない。魚といえば、すし屋のネタが頭に浮かぶ。鳥はみんな飛ぶと思っている。虫の足が6本あることや、テントウムシに羽があるのを知らない。身の回りを、きつい人工的な刺激のあるものに、囲まれているせいか、ひっそりと存在する本物に、気がつかなくなっているような気がする。自然の中で遊ばないのだから、仕方がない。 なんとか、その本物の感じだけでも、見せてやれないものかと思いながら、やっと出会ったのが、「のはらずかん」だった。 長谷川哲雄さんの絵が、あまりにもすばらしくて、思わず見惚れてしまった。小さな花が、咲き乱れる野原や川原、池や沼のほとりの風景が、まるで、そこに分け入っていくような感覚で描かれている。おまけに、昆虫や鳥も、その風景の中で、きちんと生活している。「トンボは、こんな所にこんな風にとまるんだなあ。」とか、「モンシロチョウは地面にも止まるし、アリはバッタも運ぶのか。」とか、いちいち感心する。 この「のはらずかん」をきっかけに「絵本図鑑シリーズ」の存在を知って、心が躍った。見れば見るほど芸術の域に達している。シリーズといっても、この絵本は、装丁も、形式も、文章も、もちろん絵も、一冊一冊が、独立した存在感をもっている。作者はそれぞれに、自分の持ち分野に精通しており、それを愛してやまない熱意が伝わってくる。岩崎書店の渾身の図鑑つくりなのではないだろうか。全部を揃えたくなった。 …つづきへ |
| 私の二人の娘は本が好きです。特に上の娘は、いわゆる本の虫で、常時何冊かを平行して読み、活字であれば 新聞から包装紙までなんでも読む子供でした。長じていまは言葉の研究をしています。 さて、彼女がそんなに本が好きになったのは堺谷寛子さんが主催されていた「きらきら文庫」に1歳から6歳まで通っていたからなのです。三つ子の魂百までとはよく言ったものです。 堺谷せんせいの読み聞かせを輪になって身を乗り出して聴いていた子供たちの食い入る面持ち。 |
私にとってはその情景はもう遠い昔のこととなりましたが、堺谷せんせいはその後もずっと彼らを恍惚の世界にいざなう仕事を続けています。 きっとせんせいは、子供たちのその眼差しの虜となっているのに違いないと私は思っているのです。  |