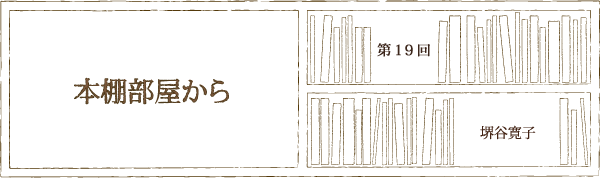| 子ども達に本を読んでいると、その表情には、話の進行に沿うように、いろいろな変化が見られる。自分は、それが楽しくて、読み聞かせにはまっていったといっていい。優れた絵本やお話であれば、必ず子ども達は反応する。大人よりずっと、子ども達の方が、絵本を見る目は確かである。よい絵本を選ぼうと思ったら、まず子ども達に読んでみることだ。その本に乗っかってくるか、入り込んでくるかは、表情を見ていると分かるが、どんな感情が動いているのか、何が心に響いているのかは、いつまでたっても謎である。
その点、子ども達の中に、ものすごく分りやすい言葉で、端的に感想をぶつけてくる子がいると、うれしくなる。そのかわり、「先生、今日のお話はイマイチだったよ」と辛辣に、軽く言われたりすることも、覚悟しなければならない。そういう時には、結構落ち込む。次は絶対に「面白かった」と言わせてやる。と意気込みながら、絵本選びをすることとなる。なんらかの表情の変化を見せる子ども達を見ると、「どうよ!この話」などといい気になれる。いやはや、大人気ないことだ。 考えてみれば、私は、絵本選びに関しては、子ども達にずいぶん勉強させられているということだ。 私達は普通、子ども達の表情から察するに、楽しい絵本とは、起伏のあるドラマチックな絵本だろうと、簡単に考えていて、どうしてもそういう絵本を選んで読むことが多い。だが、それは大きな間違いで、優れた絵本には、どんなものでも、ドラマチック要素があるのだということが、だんだん分ってくる。ドラマチック要素とは何か?はらはら、どきどきの感情を起こすだけのものではないのだろう。なんだか分らないけど、妙に頭に残るような、人の感情を何かの形で刺激するような、種を蒔く要素とでもいおうか・・・ |
 |
| 「ロバのシルベスターとまほうの小石」 |
|
この絵本は、ウイリアム、スタイグの傑作中の傑作である。 いつもそうだが、傑作絵本との出会いは、案外、ちょっとしたきっかけによる。いわゆる、琴線に触れるというやつか・・・・。 表紙の絵が目にとまる。 「ロバが、隣のブタに何かを尋ねている。ロバは、ムームーに似たワンピースを着ている。なんだか微妙にロバらしくて似合っている。向こうには、スーツ姿のロバ。こっちは、ニワトリに話しかけている。この二匹は夫婦なのかな。しかし、なんで、よりによってロバなんだ?しかも、二匹とも、とぼけているように見えて、大真面目なようだ。」 こんな風に、ぼーっと、本屋で表紙を見ていた。そのうち、ロバとブタの目が悲しそうに見えてきた。なんだか事件の匂いがする・・・・・。 急に、すごくこのお話が読みたくなった。 それが、この絵本との出会いであった。 その時はまだ、この絵本の、本当の偉大なドラマチック要素は微塵も感じていなかった。 …つづきへ |
| 文句なしのドラマチック場面が、切れ味さわやかに表現されているのは、昔話や、民話である。本屋には、数多くの絵本があり、選び放題のように思われるが、本当にしっかりと書かれた絵本は限られていると思う。
私が昔から、小さい子ども達に、よく読み聞かせている絵本に、マーシャ・ブラウンの民話絵本がある。「さんびきのやぎのがらがらどん」「もりのともだち」「ぱんはころころ」である。 ちなみに、「さんびきのやぎのがらがらどん」と「ぱんはころころ」のお話は他にも出ているが、私は絶対に、マーシャ・ブラウンの絵本で、このお話を読むことにしている。人生を生き抜いていく力を与えてくれる昔話・民話の力強さが、その絵からビンビン伝わってくるからだ。 |
 |
 |
 |
| 「さんびきのやぎのがらがらどん」 : 福音館 |
「もりのともだち」 : 冨山房 | 「パンはころころ」 : 冨山房 |
| 当たり前だが、絵本には絵があって、お話の醍醐味を視覚からも味わうことができる。マーシャ・ブラウンのこの3冊は、絵によって最高の盛り上がりを掻き立てていて、絵の役割がどんなに大事かが、非常によく分かる絵本である。
印刷に使われている色は少なく、紙も素朴。残念なことに、一般には地味な絵本と捉えられていて、なかなかお母さんたちが、この絵本の良さに気づいてくれないのが、残念でたまらない。 多分それは、絵本を読まれる側にまわって、この絵本を楽しんだことがないからだと思う。読み聞かせているよりも、読んでもらったほうが、ずっと楽しめるのは間違いない。子ども達に混じって、文字に執着せず、心を開いて、耳と目で素直に絵本に触れる。大人にとっては、結構これが難しい。 お話は、知っているはず、どうなるか百も承知。なのに、このお話のドラマチック場面の迫力は、圧倒的である。一度読んでもらえば、きつねの赤、おんどりの緑と赤、やぎのバックの水色、トロルの茶色が目に焼きつくことは、間違いない。 A4の絵本を開くと、A3の大きさの画面になるが、開いたとたんに、模造紙のように大きく見えて、どきどきはらはら感が迫ってくる気がするのは、私だけではないはずだ。 …つづきへ |
| 私の二人の娘は本が好きです。特に上の娘は、いわゆる本の虫で、常時何冊かを平行して読み、活字であれば 新聞から包装紙までなんでも読む子供でした。長じていまは言葉の研究をしています。 さて、彼女がそんなに本が好きになったのは堺谷寛子さんが主催されていた「きらきら文庫」に1歳から6歳まで通っていたからなのです。三つ子の魂百までとはよく言ったものです。 堺谷せんせいの読み聞かせを輪になって身を乗り出して聴いていた子供たちの食い入る面持ち。 |
私にとってはその情景はもう遠い昔のこととなりましたが、堺谷せんせいはその後もずっと彼らを恍惚の世界にいざなう仕事を続けています。 きっとせんせいは、子供たちのその眼差しの虜となっているのに違いないと私は思っているのです。  |